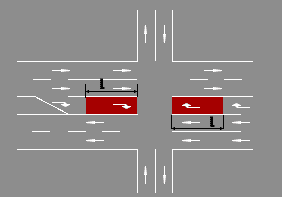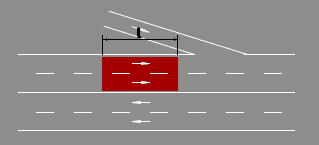樹脂系すべり止め舗装は、一般的には既設または新設のアスファルト舗装・コンクリート舗装の路面に、可撓性エポキシ樹脂をバインダーとして薄く均一に塗布し、その上に耐摩耗性の硬質骨材(黒および着色)を散布して固着させる方法で、すべり抵抗性を湿潤時にも高く発揮させることを目的とする。
このマニュアルは、既設または新設のアスファルト舗装・コンクリート舗装面に設置する場合に適用する。
樹脂系すべり止め舗装の設置場所は、交通事故の多発している箇所、または交通事故の誘発が多く予想される箇所が対象となる。具体的には、勾配、幅員、形状、見通し、地盤等の道路構造や規制、交差、離合、居住環境等の沿道状況、それに車両・人の通行密度、通行車両種類の現況と発生事故の形態・特徴等の交通事情、更にはすべり止め舗装がドライバーに対しおのづと安全運転を誘導する効果をも考慮して、適性に設置する必要がある。
車両走行における車両相互の衝突、追突、および車両自体のすべり(横すべりも含む)、失速、オーバーラン、転落等の可能性が高い地点、また交差点、狭小部、裏通り等車両通行と人の通行との競合(交路)度の高い箇所が対象となる。
目的とする地点・箇所を主要地点として、その主要地点を包含して、必要な幅員と平均的な車両走行速度による制動距離を勘案した主要地点より手前側の必要長さが迄が設置する範囲となる。
対象とした範囲を全面施工するベタ方式と、断続施工するゼブラ方式とがある。どちらも減速および制動効果を発揮するが、ゼブラ方式は段差舗装であり、断続的な体感を与えるとともに走行時に断続音を伴い、運転者に注意を喚起させる。ゼブラ方式のこの断続音は周辺に対し、騒音公害となるため、居住密度の高い区域ではベタ方式、または着色を交互にするWゼブラ方式が最適である。居眠り運転の防止、暴走族利用の回避等のためにはゼブラ方式が有用となる。
短距離で出来るだけ制動効果を高める場合には、連続した面施工(ベタ方式)を、曲線部、急傾斜部等の導入表示や、不連続性に基づく目視・体感等による注意喚起の場合には、不連続の施工(ゼブラ方式)を用いる。ゼブラ方式では、導入・接近を強調する山形減速マーク、緊張感覚をもたせるV字、千鳥等のデザインがある。
交差点、横断歩道の手前、長く続く曲線部、斜面(坂道)等ではベタ方式が一般的である。急傾斜、急カーブ部の区域では、ゼブラ方式(段差方式)で導入し、最大危険区域や地点はベタ方式で施工する。
樹脂バインダー層および散布骨材の頂部迄を含めて、通常は3.3~2.0㎜粒径の骨材を使って4~5㎜厚である。段差を大きくする場合は5.0~3.3㎜粒径の骨材により6~8㎜厚となる。
| 施工厚 mm |
骨材粒径 mm |
材料使用量 kg/m2 | ||
| エメリー | 着色骨材 | バインダー | ||
| 4~5 | 3.3~2.0 | 8 | 6.5 | 1.7 |
| 6~8 | 5.0~3.3 | 7.5 | 2.3 | |
施工部分の仕上がり(色彩)をより鮮やかにするためにトップコートをかける。黒(エメリー)および光輝性(キラキラ)仕上げの場合は、トップコートを適用しない。
ホイールベース2.6mの車両を例にとると、施工部分は2.6m以上、施工間隔は2.6m以下にとれば、前後輪どちらかは必ずすべり止め舗装の上にある。しかし通行車両のホイールベースは一定していないため特定するのは難しい。一般的によく行われている2m交互の方式では、2.6mホイールベースの車両は、85%は前後どちらかのホイールがすべり止め舗装の上にあることとなる。
代表的な例を示す。
| 施工間隔(m) | |||
| 1 | 2 | ||
| 施工 部分 (m) |
1 | 様式A | 様式B |
| 2 | 様式C | 様式D | |
| 3 | 様式E | 様式F | |
施工部分(施工区長さ)と施工感覚の組み合わせ
ゼブラ様式C・D(ホイールベース2.6m)の場合
| 様式 | 施工 部分 (m) |
施工 間隔 (m) |
すべり止め接触 | 有効 接触度 |
非接触 | 100m 振動 回数 |
必要 材料 指数 |
|
| C | 2 | 1 | 53 | 27 | 67 | 20 | 132 | 67 |
| D | 2 | 2 | 15 | 70 | 50 | 15 | 100 | 50 |
注2.有効接触度=全輪接触度+(前or後)×1/2
注3.100m振動回数;100m走行間の前・後ホイールの段差部通過回数
注4.必要材料指数;ベタ方式を100とする。
ゼブラ施工での間隔のとり方は、施行目的に合わせるのがよい。居眠り防止に対しては振動回数の多い様式を、またすべり止めを主目的にする場合は接触面積の大きい様式が有効となる。使用材料費はE様式が大であり、作業労務費はA様式が大きくなる。直線道路で高速になりがちの場合は、上記A~F様式でなく、20~50m間隔で1~2m幅のすべり止め施工を行う様式がとられている。一般的には‘C’或いは‘D’が平均的な様式となっている。
当初(昭47年頃)は骨材はエメリーに限られ黒色仕上げであったが、現在はエメリー系黒11%、炭化珪素系黒(光輝性)6%、カラー系83%(平8年集計)である。 カラー系の中では、赤褐色74%、黄土色12%、緑10%、白3%、青・その他1%となっている。
濃色の道路表面は高温になる。確認されている例を下記表に示す。
| 外気温 | アスファルト 舗装面 |
赤褐色系 | 緑色系 | 黄土色系 | 白 | |
| 周辺 | 32.9 | 62.3 | 39.8 | |||
| 濃色 | 58.9 | 58.6 | 49.6 | |||
| 中間色 | 52.3 | 52.3 | 44.6 |
注2.単位;℃
注3.神奈川県海老名市、天候:晴
すべり止め舗装は交通事故の低減を目的にしているので、カラー化は危険予知、注意喚起が第一の目的となる。これに加えて、景観(環境との調和)道路表面の昇温抑制、早期汚染の回避等から色彩が選択される。最近では交差部と流入部で、ベタ、ゼブラどちらの方式でも、光輝性骨材(炭化珪素)を加えての複数着色骨材の組合せが取り入れられている。
樹脂舗装技術協会では施工対象路面の種類および仕上げ様式と、適用骨材の粒径、施工様式、トップコートの有無等から現在18種の工法を決めている。その中で各ケースに応じて標準的な材料適正量を定めている。これを工法規格としてRPN番号をつけて区分している。樹脂舗装技術協会工法規格(別ページ)の通りである。
(RPN;Resin Pavement Neat)
| 6-1.直線部 | 6-2.交差部 | 6-3.曲線部 | 6-4.特定仕様 |
| 1)横断歩道手前 2)鉄道踏切手前 3)右折ゾーン 4)合流地点手前 5)傾斜部(坂道) |
1)交差部 2)三叉部 |
1)曲線部基本 2)カーブ手前 3)カーブ地点 4)組合せ |
1)暴走族対策 2)歩道、通学路、遊歩道 3)ゼブラパターン 4)Wゼブラ |
1)横断歩道手前及び、2)鉄道踏切手前
(推奨工法 RPN-1-2,3,4)
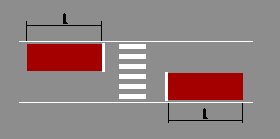
施工対象例
|
 |
| 交差点流入部 (推奨工法 RPN-1-2,3,4)  |
交差点内部 (推奨工法 RPN-1-2,3,4) 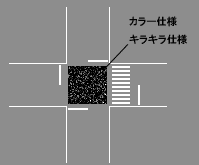 |
参考
|
 |
2)カーブ手前 <目的>減速効果
(推奨工法 RPN-7,7-2,8,9)
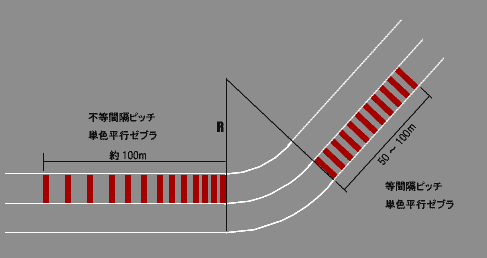
3)カーブ地点 <目的>スリップ防止
(推奨工法 RPN-3,4)

4)組合せ <目的>スリップ防止・減速効果
(推奨工法 RPN-7-2,8,9) (推奨工法 RPN-3,4)

1)暴走族対策 <目的>暴走族の追放・ゼロヨン対策
(推奨工法 RPN-10)

設置本数は交通事情にて考慮する(5~10本/1箇所)
2)歩道、通学路、遊歩道 <目的>歩行者の安全確保・駐車禁止の喚起・歩車道分離
(推奨工法 RPN-13,15)
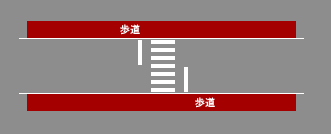
3)ゼブラパターン <目的>段差効果、注意喚起
(推奨工法 RPN-8,9)
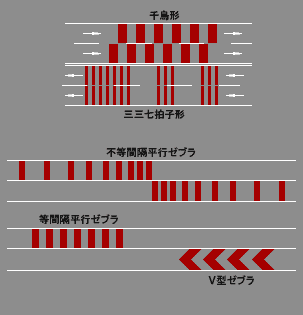
4)Wゼブラ <目的>スリップ防止・視認性向上効果
(推奨工法 RPN-8-2)
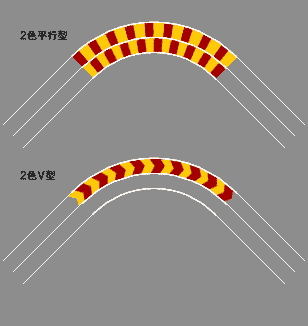
| 注. | 一般に曲線部の手前で減速し、曲線中央部で加速する。自動2輪車の場合、この加速時に段差舗装に基づく走行不安定を招くことがある。これを避けるため、全面方式、あるいはWゼブラ方式が望ましい。 |